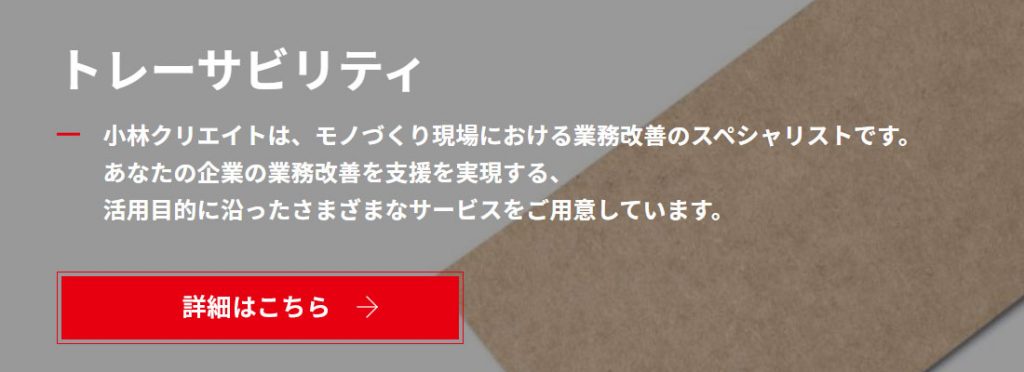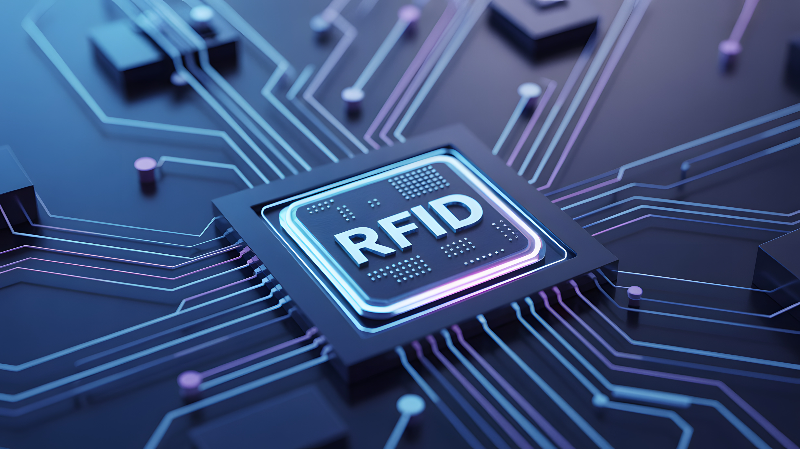トレーサビリティシステムとは?
基礎知識や導入メリットを解説

製造業にとってトレーサビリティは非常に重要であり、トレーサビリティシステムを導入することで、データの正確な記録・追跡や品質の維持・向上などが期待できます。一方で、導入時には課題もあるため適切な対策を実施する必要があります。
本記事では、トレーサビリティシステムの必要性や導入のメリット、導入時の課題と対策を解説します。
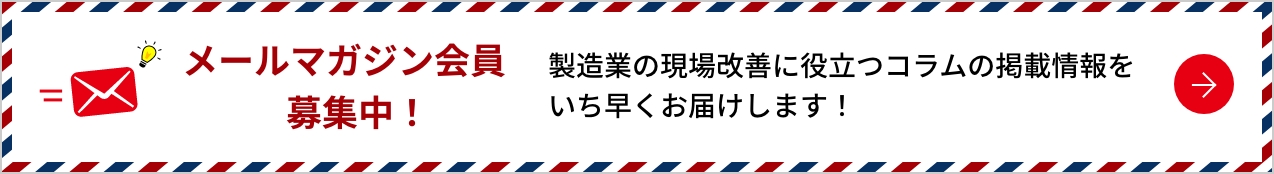
トレーサビリティシステムとは
トレーサビリティシステムとは、製品の生産から消費者に届くまでの過程を記録・追跡し、必要に応じてその履歴を確認できる仕組みのことです。製品に付けられたバーコードや二次元コード、RFタグなどを活用し、原材料の調達、生産工程、流通経路、販売先などの情報を記録・管理します。
製品の品質管理やリスク管理などの目的で、製造業をはじめ食品業界や医薬品業界など幅広い分野で活用されています。
そもそもトレーサビリティとは
トレーサビリティには大きく分けて、2つの種類があります。
・チェーントレーサビリティ
サプライチェーン全体の原材料、部品、製品などの流れを追跡する仕組みです。具体的には、原材料の調達から製造、加工、流通、販売、消費、さらには廃棄までの全過程を記録・管理します。
「トレーサビリティ」と言えば、一般的にはこちらを指します。
【特徴】
複数の企業や主体をまたいで情報を追跡するため、広範囲にわたる履歴管理が可能です。生産者は自社製品がどこで加工、消費されたかを把握でき、消費者は製品の生産地や流通経路を確認できるため、安心して製品を購入できます。
・内部トレーサビリティ
特定の企業・メーカーや施設内での製品や部品の移動履歴を追跡する仕組みです。工場や倉庫などの限定された範囲での情報管理を指します。
【特徴】
部品の仕入れ、製品の組立、検品結果、出荷先などの情報が追跡可能です。主に品質管理や作業効率の向上を目的とし、各工程で問題が発生した際に迅速に対応できます。
まとめると、チェーントレーサビリティはサプライチェーン全体を対象とし、広範囲にわたる履歴管理を実現する一方で、内部トレーサビリティは企業内を対象としており、品質管理や効率化に特化しているという違いがあります。
トレーサビリティシステムの必要性
トレーサビリティシステムは、以下の点から製造業において必要とされています。
・品質管理の向上
製品の不具合が発生した際、迅速に原因を特定し、問題のあるロットを効率的に回収できます。
・リスク管理と安全性・信頼性の確保
問題発生時に迅速な対応が可能となり、被害を最小限に抑えられます。また、配送ルートを明確にすることで製品の品質や安全性を保証し、消費者からの信頼性の向上に寄与します。
・効率化とコスト削減
データの一元管理やリアルタイムでの在庫管理により、工程の無駄を洗い出し、改善につなげられます。これにより業務効率が向上し、在庫の維持・管理コストや人件費などを削減できます。
トレーサビリティシステム導入のメリット
トレーサビリティシステムを導入することで、以下のメリットを得られます。
各工程のデータを記録・追跡できる
製造・加工・流通など、製品がたどる各工程のデータをリアルタイムで記録・追跡できるため、どの工程でどのような作業が行われたのか、いつ誰が関与したのかなど、詳細な履歴情報の取得が可能となります。
万が一トラブルが発生した際にも、迅速に原因を特定し、的確な対応がとれるため、業務の透明性と信頼性が高まります。
在庫の一元管理が可能になる
製品や部品ごとの流通状況やロット情報などを一元的に管理できるため、在庫の過不足をリアルタイムで把握可能です。複数の拠点や工程にまたがる在庫管理も容易になり、無駄な在庫の削減や、欠品・重複発注の防止につながります。
また、需要予測や生産計画の精度も向上し、効率的な物流体制の構築に貢献します。これにより、管理コストの抑制や生産性向上を実現できます。
品質の維持・向上に寄与する
各工程のデータが記録されることで、品質に関するトラブルの兆候や不具合の発生傾向を早期に検知することが可能です。これにより、適切な再発防止策や改善活動を行えるようになるため、製品全体の品質レベルを維持・向上できます。
また、一定の品質基準に基づいた製造や検査が行われていることを裏付ける証拠としても活用でき、顧客や取引先、消費者への信頼性アピールにもつながります。
トレーサビリティシステム導入時の課題と対策
一方で、トレーサビリティシステムの導入時には以下のような課題もあり、対策が必要です。
データの整合性と信頼性を確保する必要がある
トレーサビリティは「正確なデータ」があってはじめて機能する仕組みであり、現場での記録ミスや入力漏れ、形式のバラつきがあると、整合性や正確性が失われるおそれがあります。特に、サプライチェーン全体で情報を統一的に管理することは容易ではなく、企業や拠点ごとに異なるデータ形式や管理基準が併存していると、情報の断絶や矛盾が発生する可能性があります。
また、情報の改ざんや誤りを防ぐ仕組みも必要です。
対策としては、入力時点での自動チェック機能や、バーコード・RFIDといった自動認識技術の活用が有効です。
サプライチェーン全体での体制を構築する必要がある
自社だけでなく、仕入れ先、製造委託先、物流業者、販売先など、サプライチェーンに関わるすべての企業や部門が協力し、情報を共有する必要があります。しかし、関係者間での認識のズレが生じやすく、前述のようにデータ形式や管理基準の統一も課題となります。
対策としては、データの統一や連携のためのルールづくり、信頼関係の構築や認識の共有を図っていくことが重要です。また、参加企業に対してメリット(リスク低減や取引先評価の向上など)を明示し、協力を促す仕組みを整えることも効果的です。
初期コストの負担がかかる
システム導入にあたっては、ハードウェア(バーコードリーダー、RFタグなど)やソフトウェアの購入・開発、ネットワークインフラの整備、人材教育など多くの初期費用がかかります。特に中小企業では、この投資が大きな負担となることがあります。加えて、導入後のシステムの運用・維持費用や改修コスト(必要な場合)も無視できません。
対策としては、クラウド型のサービスを活用して初期投資を抑える方法や、段階的に機能を導入して負担を分散する方法などがあります。
トレーサビリティシステムを活用しよう
トレーサビリティシステムを導入することで、各工程のデータの記録や追跡が容易になり、在庫の一元管理も可能となるため、品質管理やリスク管理、コストの削減などを実現できます。
一方で、サプライチェーン全体での協力体制の構築や、データの整合性や信頼性の確保といった面で課題が生じることもあるため、段階的な導入計画の立案や社内外との十分な調整が不可欠です。
トレーサビリティシステムの一つに、RFIDを活用したソリューションがあります。
RFIDによりサプライチェーンの各段階で情報を読み取ることで、製品が「いつ、どこで、誰によって」生産・流通したかを自動的に記録し、リアルタイムでの「みえる化」を実現します。
以下の資料では、トレーサビリティを含めRFIDで製造現場の課題を解決する方法を詳しく解説していますので、ご興味のある方はご覧ください。
お役立ち資料はこちら

お役立ち資料
改善ネタ集
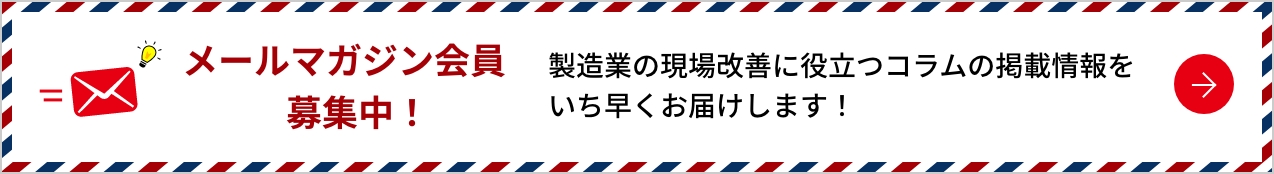

倉庫管理における役割やメリットを解説

とは? メリットや課題、
トレーサビリティとの関係性について解説

「みえる化」する目的とメリット
実績収集システムの導入事例をご紹介