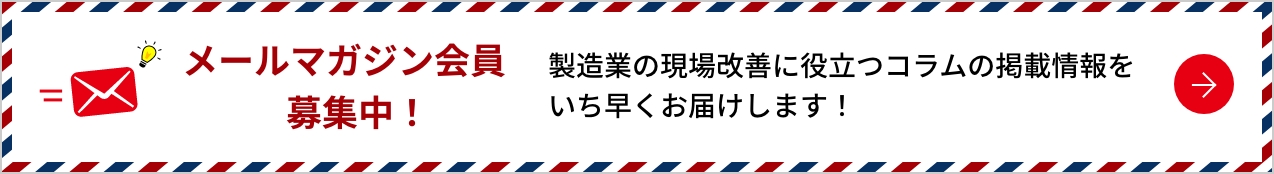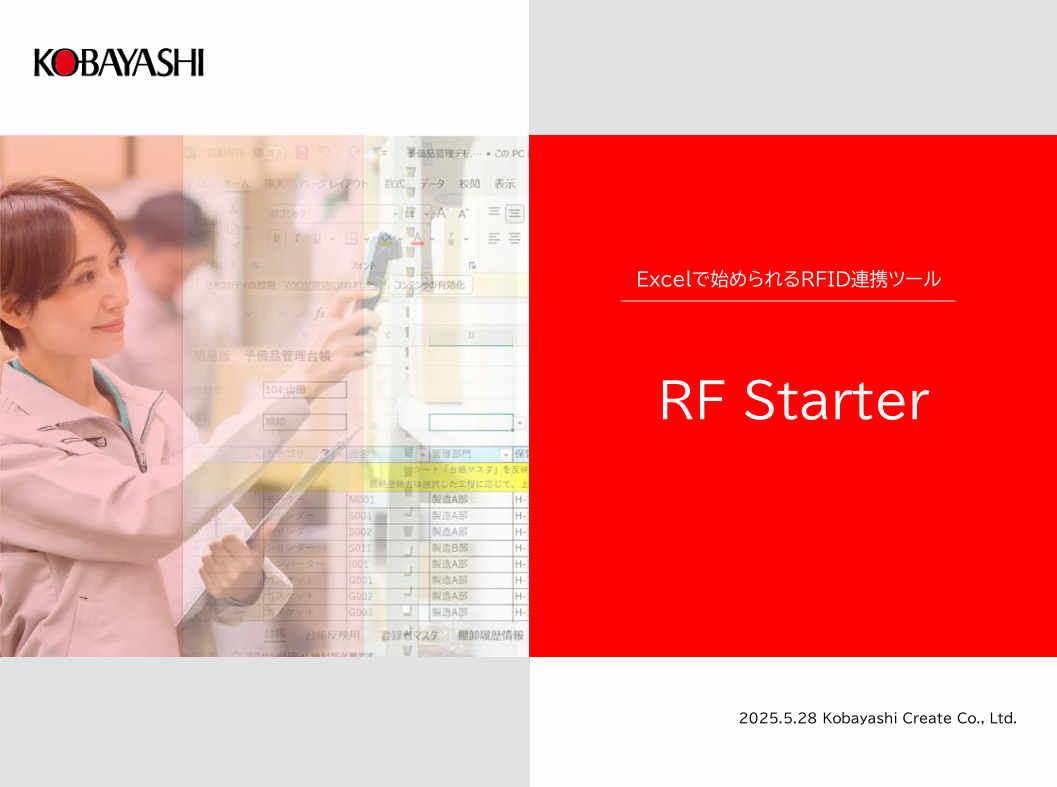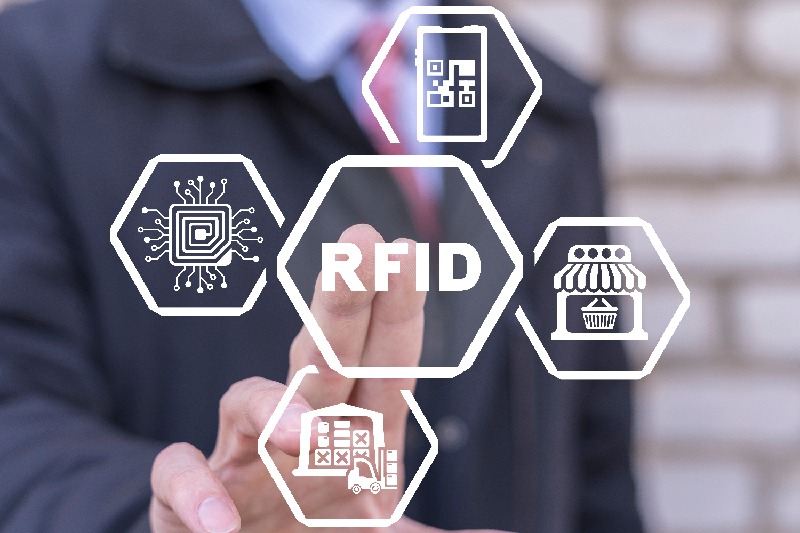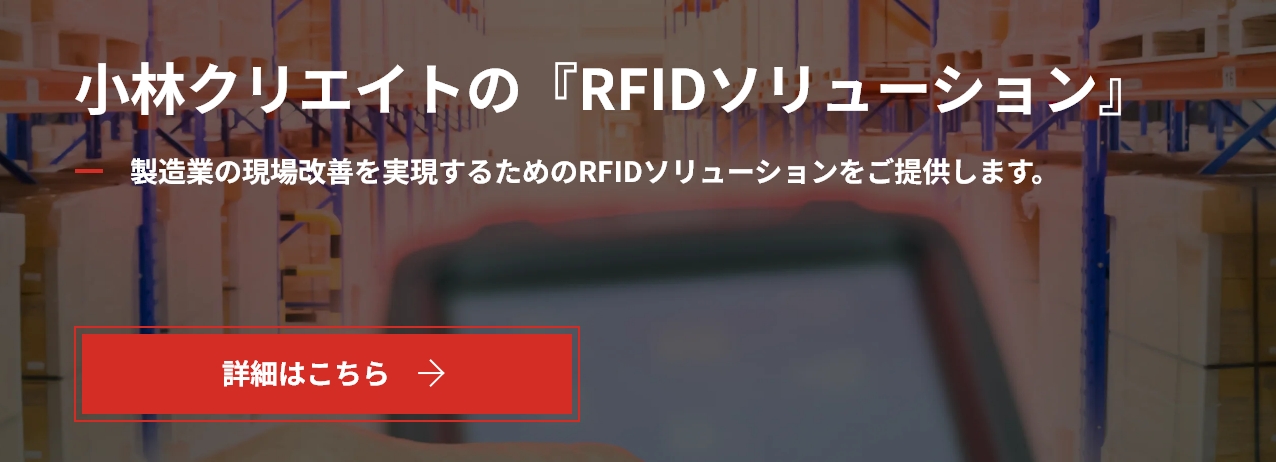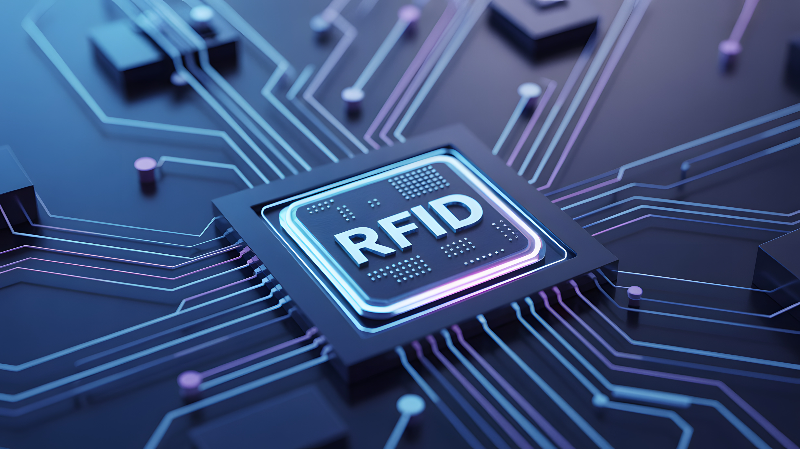【製造業向け】RFIDでよくある質問Q&A

RFIDは、RFIDリーダライタやRFタグなどさまざまな要素で構成されており、種類によって特徴が異なります。また周波数帯によって読み取り範囲が異なる、出力によって電波利用申請が必要になるなど、多くの留意事項があるため、導入前にRFIDの基礎情報を知っておくことが大切です。
そこで本記事では、RFID導入の際に押さえておきたい事項をQ&A方式で解説します。
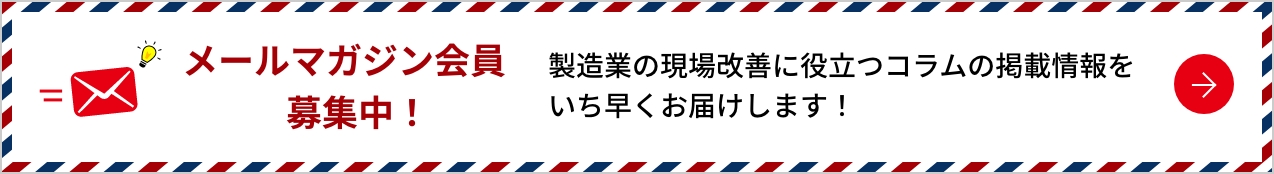
RFIDの導入で失敗しないために
RFIDは製造や物流の現場において、業務効率の向上やコスト抑制、ヒューマンエラーの防止など多くのメリットをもたらします。しかし、現場の環境や用途に応じて最適な機器の種類は異なるため、単に導入するだけでは期待した成果は得られません。
社内で現場の課題を整理した上で導入目的を明確にし、段階的な導入・検証を行うことが成功のカギを握ります。そのため、RFID導入検討時によくある疑問を解決しておくことが重要です。
次章では、RFIDの導入時に知っておきたい事項をQ&A方式でご紹介します。また、最後にRFIDの導入で失敗しないポイントもご紹介します。
RFIDでよくある質問【基本編】
RFIDリーダライタにはどのような種類がある?
RFIDリーダライタには「ハンディタイプ」と「定置型」があります。
・ハンディタイプ
アンテナとRFIDリーダライタが一体となっており、持ち運んで使用することが可能です。比較的近距離で静止している製品に取り付けたRFタグを読み取る際によく使用されます。
ハンディタイプは「一体型」「セパレート型」に分類されます。
一体型はハンディターミナルにRFIDリーダライタを組み込んだタイプです。操作は十字キーやテンキーなど物理キーで行います。
セパレート型は、RFIDリーダライタとアプリが搭載されたスマートフォンなどのモバイル端末が分離されているタイプです。RFIDリーダライタとモバイル端末は、Bluetoothでペアリングして利用します。
・定置型
特定の場所に設置して使用するタイプです。出入口や動線などの読み取りエリアをモノが通過した時、RFタグを自動的に一括で読み取れます。
定置型には主に「卓上型」と「据え置き型」があります。
卓上型は机やカウンターなどに簡単に設置でき、ハンズフリーで利用が可能です。小売店や図書館などでよく利用されています。
据え置き型は天井や壁、床などに設置するタイプであり、長距離の読み取りに用いられるのが一般的です。
RFIDリーダライタの種類についての詳細は以下記事で解説しています。
RFタグにはどのような種類がある?
RFタグには「パッシブタグ」「アクティブタグ」「セミパッシブタグ」の3種類があり、目的によって使用するRFタグが異なります。
・パッシブタグ:RFIDリーダライタからの電波を動力源として動きます。
・アクティブタグ:電池を内蔵しているタイプのRFタグです。
・セミパッシブタグ:通常時にはパッシブタグとして動作し、必要な時のみ内蔵電池を用いて動作を補助します。
一般的なRFタグ/ラベルは、金属が近くにあると電波が干渉してうまく動作しない性質があるため、金属類に近接する環境では金属対応型のRFタグを選ぶ必要があります。
その他、高温環境や水に濡れやすい環境など、使用する環境に対応したものを選ぶことが重要です。
RFタグの種類や各RFタグの使用環境についての詳細は以下をご覧ください。
RFタグにはどのような情報を書き込める?
RFタグには、製品識別番号、製造日、品質情報、追跡情報などの情報を書き込めます。ただしRFタグの種類によって記録できるデータ量は異なります。
情報を書き込む際には、RFIDリーダライタやRFIDプリンタが必要です。少量のRFタグへのデータ書き込みを行う場合はRFIDリーダライタで対応可能ですが、書き込むデータ量が多い場合や自社発行が必要な場合にはRFIDプリンタが利用されます。
RFタグに書き込める情報について詳しくは以下記事をご覧ください。
RFIDでよくある質問【技術編】
電波が届く範囲なら読み取りや書き込みは可能?
RFIDは電波が届く範囲内であれば、基本的にはデータの読み取りや書き込みが可能です。ただし、交信距離や性能は使用する周波数帯や電波出力などによって異なります。
周波数帯に関しては、HF帯の交信距離は50cm程度、LF帯は1m程度、UHF帯は5~10mほどです。
電波出力に関しては、出力が高いほど交信距離は長くなります。
このほか、アンテナの大きさや金属製の障害物が近くにあるかといった使用環境によっても変動します。
特に製造現場では、金属製の設備、部品、治具、棚、さらには水分や各種機器が発するノイズなど、電波を遮る、乱反射させる要因が非常に多く存在します。そのため、「電波が届く=必ず読み書きできる」とはならず、安定した通信を確保するためには、導入環境を詳細に調査した上でのRFタグの選定、アンテナの設置場所や角度の調整が不可欠です。
以下の記事ではRFIDの交信距離について解説していますので併せてご覧ください。
特定のRFタグだけ読み取れる?
RFIDは、特定のRFタグだけを読み取れます。
RFIDリーダライタやミドルウェア(制御ソフト)にはフィルタ機能があり、これを使うと読み取り範囲内に複数のRFタグがあっても、「特定のEPCコードを持つRFタグのみを読み取る」「メモリ領域に特定の製品コードが書かれたRFタグだけ読む」といった処理が可能です。
ただし、EPCコードに関しては、複数のRFタグに同じコードを書き込まないようにして一意性を保つ必要があります。
EPCの詳細は以下をご覧ください。
また、RFIDリーダライタとRFタグとの間の通信強度の指標であるRSSIの範囲を設定することで、特定の距離の範囲内にあるRFタグを読み取ることもできます。
RSSIの詳細は以下をご覧ください。
日本と海外で同じRFIDを使用できる?
日本と海外で同じRFIDをそのまま使用できるケースもあれば、使用できないケースもあります。
周波数帯に関してみてみると、HF帯(13.56MHz)はほぼ世界共通です。LF帯(135KHz以下)もLF自体の周波数範囲は国際的にほぼ同一であり、125〜135KHzで標準化されていることが多いため、基本的には世界各国での互換性は高いです。ただし、各国の電波規制や使用条件に応じて微調整が必要な場合もあります。
UHF帯は国ごとに割り当て周波数が違うため、海外の特定の地域向けに製造されたUHF対応機器を日本でそのまま使うことはできません。
また、技術基準適合試験をクリアしている証明がされていない(技適マークが付いていない)RFIDリーダライタは電波法違反となり、日本国内では利用できません。加えて、電波出力が1Wを超える機器は日本では利用が禁止されています。
RFIDでよくある質問【導入編】
RFIDの活用事例は?
RFIDは製造業の現場においてさまざまなシーンで活用されています。
具体的な活用例としては以下があります。
・在庫管理の効率化
RFIDを用いて在庫管理を行うことで、各工程の在庫数量の一元管理を実現し、余剰在庫をなくし在庫切れも予防できるようになります。
・通い箱・パレットの紛失防止
RFタグを通い箱・パレットに取り付けることで、出荷時にRFタグを読み取って出荷履歴を確認できるため、どの通い箱・パレットがどこに出荷されたかを正確に把握できるようになります。返却時にもRFタグを読み取ることで回収漏れを防ぐことが可能です。
・金型管理の効率化
RFタグを用いた金型管理システムを活用することで金型をシステム上で管理でき、PCやタブレットで手軽に金型の貸し出し状況や置き場を確認できるようになります。
その他、「工具の持ち出し管理の見える化」や「材料の先入先出の徹底」など、多くの活用事例があります。
各事例の詳細はこちらをご覧ください。
RFIDのコストはどのくらい?
RFIDの導入コストを構成要素や機器別にみると、主に以下の通りです。
・RFタグ
標準的なRFタグの価格は、1枚10円~30円台程度です。耐熱・金属対応タグの場合1個数百円~数千円程度と、用途によって価格が大きく変わります。
・RFIDリーダライタ
ハンディ型や据え置き型の本体価格は20万円~30万円程度です。ゲート型の場合、ゲートアンテナの費用に加え工事費用も必要です。
・ソフトウェア
メーカーや仕様により異なります。
その他、周辺機器としてRFID対応のラベルプリンタを導入する場合は50万円~100万円程度かかります。
RFIDにかかるコストについての詳細は以下記事で解説しています。
RFIDの導入に電波利用申請は必要?
250mW超1W以下のRFIDリーダライタを利用する場合には、総務省に電波利用申請を行う必要があります。特に交信距離の長いRFIDは高出力のRFIDリーダライタを使用するため、申請するケースが多いです。
なお、「特定小電力」に分類される250mW以下のRFIDリーダライタであれば申請は不要です。
RFIDの電波利用申請についての詳細は以下記事で紹介しています。
RFIDについてのご相談は小林クリエイト
本記事でご紹介したように、RFIDにはさまざまな種類があり、情報の読み取りや書き込みを行う上でも知っておきたい事柄が数多くあります。これらのポイントを押さえ、自社に最適なRFIDを選定しましょう。
小林クリエイトでは、RFID運用のスモールスタートに最適なソリューション「RF Starter」を提供しています。「RF Starter」 はExcel運用のまま手軽にRFIDを導入でき、3ステップで導入が可能です。
テンプレートを利用することで低コストでRFIDを導入でき、初期投資を抑えつつ段階的に運用を拡大できます。
以下の資料では、「RF Starter」の特徴や活用例などを詳しく解説していますので、ご興味のある方はご覧ください。
また、こちらの資料ではRFIDの導入で失敗しないためのポイントをまとめていますので、併せてご覧ください。
お役立ち資料はこちら

お役立ち資料
RFID導入における
ポイントとは?